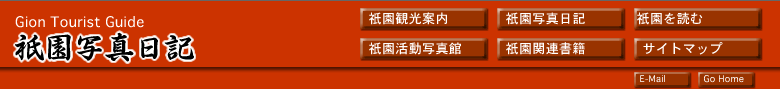
2004年08月12日
花見小路通り


祇園において、四条通が東西のメインストリートとするなら、花見小路は南北のメインストリートで、ほぼ祇園の中央を南北に横断して北は三条通 り、南は安井北門通りまでの全長約1kmの路です。
花見小路は四条通りを堺にして、北側と南側では町並みの雰囲気が大きく異なります。 北側はスナックやクラブなどが入居するテナントビルが建ち並び、 南側は竹矢来に格子作りの茶屋や料理屋が建ち並びます。

都をどりの時期の花見小路南側

祇園甲部歌舞練場
古い町並みが素晴らしい花見小路南側ですが、その歴史は以外に新しく、今に言う祇園町南側一帯は明治までは建仁寺の寺領で、明治 初期の廃仏毀釈によって寺領が狭められ、明治7年に祇園甲部お茶 屋組合が7万坪を買い上げ、花街として整備されました。 四条通りの南東角には有名な一力茶屋があり、通りを進むと両側にはお茶屋や料理屋などの町屋が並び、京都らしい風情の景観となります。

突き当たると臨済宗総本山建仁寺の境内になり、竹垣の中でも非常に代表的な垣根の一つである建仁寺垣が見られます。

四条通りを挟んで北側の花見小路には東に「祇園東」と呼ばれる京の五花街の一つがあり、南側は昭和初期まで祇園甲部の中で、もっとも栄えた新橋、富永町、末吉町がある事から夜の祇園のメインス トリートとして栄えたました。
それが災いし、戦後雑居ビルが乱立、スナックやクラブがたくさん入居し、残念ながら情緒の無い煩雑な町並みとなってしまいました。しかし平成13年春にはモダンな街灯と洋風の石貼り歩道が整備され京都一の歓楽街として、毎夜賑わってます。
 <
<
新門前通り

通り名からも判るように、この通りは浄土宗総本山知恩院へと続く門前通りで、西は川端通りから東は東大路まで全長約500メートルあります。この僅か500m間に美術商、古美術商が20数件が立ち並ぶ事から祇園(京)の美術ストリートとなっております。

縄手通りからの入口

新門前が古美術の町として登場するのは明治中頃。当時、外国人宿泊客の多い円山の「佐阿弥(さあみ)」や蹴上の「都ホテル」が近隣にあった事から、ちょうどその中間の新門前が彼らの散策通となっておりました。この外国人に目をつけた骨董の貿易商達が、こ ぞって新門前に進出してきたそうです。
日露戦争の頃には、妙法院、智積院がロシア軍の捕虜達の収容所となっておりました。 彼らはなんと自由行動を許されており、お金も持っていたので、新門前に来ては骨董を買っていったそうです。
そういった歴史があり新門前は外国人観光客に人気の通りとなっていったので、古美術商の丁稚も番頭も英会話の修行が必須。 中には2、3カ国語を話す猛者もおられました。 新門前に訪れた海外の有名人には、英国王室のコンノート殿下、世紀の恋で知られるウィンザー公、大リーガーのベーブ・ルース等、 多数おられます。近年ではラルフ・ローレンやティナ・ターナーなどもおいでになられました。

美術商の2代目たち若い世代が音頭を取って作ったのが、「だるま」マークでおなじみの「新門前ショップリーグ」。 シンモンゼンのイメージアップをはかるため海外向けにパンフレットを制作したり、海外研修など熱心な活動が功を奏し、外国人観光客からは 「ダルマストリート」と呼ばれ親しまれております。


→このコーナーの制作にあたり、新門前の古美術商「稚松軒今井」様に全面的にご協力頂きました。 ありがとうございます。
稚松軒今井ホームページ ▼
http://homepage2.nifty.com/chishoken/

切り通し

白川南通りから四条通りまでわずか150m程度の小道です

寛文年間(1661〜73)公許の郭として正式に開かれた祇園町の内外六 町である「富永町」と「末吉町」「本吉町」を横断する為、花街と してもっとも栄えた通 りの一つでしたが、戦後になると、それが災 いして廃業したお茶屋跡にビルが乱立、現在はビルの間に京町屋が挟まって建っているというあまり風情の無い通りになりました。

夜の切り通し

しかしながら、祇園の中では比較的古い通りですので、現存するお 茶屋や置屋、料理屋は歴史のある所が多く、京の鯖寿司を全国レベルの知名度に押し上げた「いづう」などの名店もこの通りにあります。 テナントビルにはスナックやクラブが入居し、夜の賑わいは昔と変わらず続いてます

末吉町通りを過ぎると、白川南通りへ至る僅か20mの部分は急に 大人3人が並ぶのがやっとの狭路となり、通りの風景が一変します。 アスファルト道路が石畳となり、格子窓と犬矢来の美しい京町屋がならんだ素晴らしい景観となります。


巽橋の上から眺める白川のせせらぎは、源流を琵琶湖に持ち、京都疎水から流れて来てます。


巽橋を渡ると辰巳稲荷がこじんまりと祀られ、地域の人々の信仰を 集めています。
2004年08月06日
四条通り


京のメインストリートと言っても過言では無い四条通りは、後ろに 東山を抱く八坂神社から西山を抱く松尾大社まで全長約7キロの路 です。 歴史は平安京までさかのぼり、古記には四条大路と記されておりま す。 京都の東西にまたがる大路ですから、門前町、繁華街、ビジ ネス街などいろんな顔を持っているのが特徴でしょう。
歌舞伎発祥の地 碑(地図マーク2)

四条大橋東詰には京阪電鉄の四条駅があり、阪急電鉄京都線の河原 町駅への乗換客で朝夕の通 勤時間帯には沢山の人通りがあります。
出雲の阿国石像(地図マーク1)

またこの地は1600年代、四条河原で出雲の阿国がかぶき踊りを踊っ たのがルーツとされる歌舞伎の発祥の地と言われ、現在でも現存する最古の歌舞伎座である南座があり、年末に行われる顔見世興行は京の年中行事として、日本全国の歌舞伎ファンに親しまれてます。
顔見世興行のまねきが上がった南座


鴨川東岸から祇園石段下までの約500mの部分は八坂神社の門前町としての色彩 が強く、飲食店や土産物、京菓子、京漬物などの有 名店が多く、中でも花街祇園を抱える事から、和装用品の店が目立 ちます。 このような店が加盟した祇園商店街では京の町にマッチ する和風のアーケードや鉄柵(ガードレール)を整備して祇園散策 をさらに楽しんで頂けるように努力しております。

四条通りに面した店はその多くが観光客向けの店の為、午後8時頃には大方の店が閉まってしまい、夜になると歓楽街である花見小路や富永町とは対照的にひっそりとした姿になります。

石塀小路



八坂神社の正門である西楼門を出て下河原通りを南に下がり3筋目 (もしくは4筋目)に左手に折れる小さな路地へ入る道があります。

路地へ入ったとたん両側に並ぶ町屋の基礎部分の石垣がまるで石塀のように見えます。 石塀小路という名前の由来が容易に想像出来ます。 京都はわりと坂の少ない町なんですが、ここら辺は東山のふもとですから勾配がけっこうあり、建物の基礎部分を大きくとってるんでしょう。 路に敷き詰められた石畳の一部は昭和50年代に廃止された京都市電の敷石を移設したそうです。

小路の両側には料亭や旅館、スナックが建ち並び、祇園の奥座敷として粋人に愛されてます。 歴史は意外に新しく大正初期に誕生したとか。 祇園にある多くの路が昔の情緒を失っている中、石塀小 路は伝統建築物保存地区に指定されてますから昔の風情をしっかり 残してます。一時期いわゆるお妾さんの家が多かった事から「お妾 通り」なんて呼ばれていた事もあったようです。 また、その絶好のロケーションから雑誌等によく取り上げられるものの、入口が見つけにくいのか人が少なく情緒的な雰囲気を味わえます。 路は右に折れ左に折れ袋小路?と思いながら数回曲がった所で高台寺通りへと抜けます。 夕暮れに歩くと、料理屋や旅館の看板が薄ぼんやりと光りさらに情緒が高まります。
