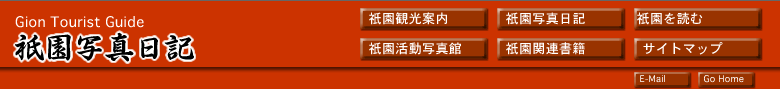
2001年12月24日
祇園の師走
師走恒例の顔見世も始まり、何とのぅ気忙しい季節となりました。始業式の話をしてたんがついきんののようどす。見たら舞妓ちゃんの簪(かんざし)にまで招木が上がっとります。この簪、花街総見の日ぃに自分の好きな役者はんの楽屋へたんねて行って書いて貰うんどす。
「○×ちゃん、あんた誰に書いて貰うん?」
「そらやっぱし、襲名しはった三津五郎はんやろ」
「そうかぁ、けど混んでんのとちゃう?うちは、楽屋廻って空いてそうなとこにしとくわ」
舞妓ちゃん、皆がみな歌舞伎好きとは限らしまへん。中にはあんまり興味ない妓もいたはります。そんな妓にとったら桟敷ちゅう晴れがましいとこで観劇するのんはほんま苦痛らしおす。だんだんと眠とぉなって来て、しまいに舟を漕ぎだす妓も中にはいたはります。横の妓がつっついて起こしたげんのどすけど、しばらくしたらまたコックリ、コックリ。舞台の役者はんはしっかりとその妓を見とります。後でお座敷に呼ばれたとき、しっかりと嫌みを云われんのやそうどす。
十三日は事始め、朝から門前のおっしょはんの家には芸・舞妓ちゃんらが次々と顔を出さはります。けどこの日ぃは紋付やのうて普段のお稽古着どす。それでも外にはカメラ小僧が山ほど集まって来たはります。この人ら平日の朝からこんなとこ来てて、何の仕事したはんのやろかて時たま思うんどすけど・・・「おめでとうさんどす、おたのもうします」ぎょうさんの鏡もちが紅いもうせんのひな壇に飾られた部屋で、おっしょはんにご挨拶すると、おっしょはんからは「来年もおきばりやす」ちゅう励ましの言葉を添えて祝儀の舞扇をくれはります。
この「おきばりやす」ちゅう言葉、決して自分よか上の人に云うたらあきまへん。「頑張って」ちゅう意味なんどすけど、これは上の者が下の者へ使う言葉どす、間違うてお姉さんにでも云うたりしたら「ちょっとあんた、誰にもの云うてはんのえ。ほんま躾けの悪い妓やわぁ、姉さんの顔が見てみとぉおす」ちゅうてえらい叱られますえ。下の者が上の者を見送るときには「行っといやす、姉さん」迎えるときは「お帰りやす、姉さん」、「お疲れやす、姉さん」ちゅうとこどっしゃろか。
昔の花街は大晦日まで営業したはって、舞妓ちゃんらもきばったはったんどすけど、最近はその年に貯めておいた公休を使うて(毎月2回ある公休日に働いて、代休を貯めておく)クリスマス過ぎには早々と帰ってしまう妓がほとんどどす。昔やと、大晦日の日ぃには「お事多さん・おことぉさん」ちゅうて舞妓ちゃんらがお世話になったお茶屋はんへ挨拶まわりをしたもんどす。で、お茶屋はんの方からは来年もおきばりやすちゅうて福玉をくれはんのどす。ちょっと前の写真を見たら、この福玉をぎょうさんぶら下げて微笑んでる舞妓ちゃんが写っとります。
あと、大晦日ちゅうたら「白朮参り」どすなぁ。この日ぃと祗園祭の宵山だけ、京の娘さんはなんぼ帰りが遅うなっても叱られしまへんのどす。特に白朮参りは夜中に出かけてそのまま初詣でちゅうパターンどっさかいに元旦から朝帰りちゅうことになります。うちらの頃は、着物姿がたんといたはって、髪も結うたはりますさかい、うっかり寝たら潰れてしまうちゅうて徹夜する娘はんが多おした。
境内で売ってはる吉兆縄を買うて、おけら火の火床から火ぃを移して家まで持って帰るんどす。そんとき火ぃが消えんように皆くるくると回してはんのどす。車に乗ったときはウィンドーにはそんどいたら大丈夫。もちろん、電車内に持ち込んでも文句は云われしまへん。で、その火で雑煮をこしらえる。ちゅうのがふつうなんどすけど、悪い子は家帰りまへん。おまけにおけら火で煙草をつけたら、肺ガンにならへんとか何とか云いながら、どこぞの飲み屋はんで燃え尽きてしまうのが恒例どした。