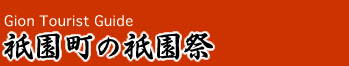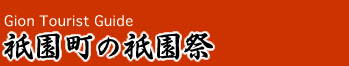花傘巡航
7月24日 午前10時〜1時頃 八坂神社〜市役所前〜八坂神社
|

|
後祭り(先の祭は17日)のトップを飾る 花傘巡航が行われました。
古い祇園祭の形式を今に伝える巡航の列には、花車や獅子舞、鷺舞い、子供神輿、祇園太鼓、先斗町の綺麗処などその他多数の団体が参加しています。
1キロメートルにも及ぶであろう巡航の列が八坂神社--市役所前--八坂神社のコースを約2時間半かけて歩きます。
花傘巡航は山鉾巡航が17日に一本化された昭和40年代に、後祭りが衰退するのを防ぐ為に開始された祇園祭の古い形態を再現したものです。
|
これが 花車です。
祇園祭の代名詞「山鉾」の原形となったもので、山鉾に比べるとずいぶん小さいですが、数基あるうち、それぞれに趣向を凝らした飾り付けがされております。 |

|

|
先斗町の綺麗処の花車です。
芸、舞妓さんの姿が見えます。
お暑い中のお着物大変でしょうね。ごくろうさまです。
|
八代目の目を引いたのがこの行列
京都織物卸商業組合の花傘娘の列。
モデルさんにでもお願いしているのでしょうか?
べっぴんさん(京都弁--美しい人の意)ばっかりです。
先斗町の綺麗処より綺麗、、あ、口がすべった
|

|